トラナビ通信
トラナビ通信 | 飲食店開業支援ならトラナビ | 飲食店の開業・独立支援ならトラナビ
トラナビ通信
-
トラナビ通信2022.08.10
出店場所の選定間違っていませんか?
開業を進める上で、出店場所の選定は極めて重要です。自身がどの様な業種でお店を出すか、どの様なターゲットを獲得するか、基準は様々です。今日は立地による、出店のメリットやデメリットについて、大きく3つに分けてそれぞれお話ししたいと思います。1.繁華街(駅近)「繁華街」のメリット・自然に多くの人が集まるので、通りすがりの来客を見込める。・宴会客を見込め、客単価も比較的高い。少人数でも回転率が良い。・仮にお店に人気が無かったとしても、おこぼれで集客できる。「繁華街」のデメリット・賃料が高く、初期投資やランニングコストで圧迫される可能性がある。・競合店が多いので経営戦略をしっかり立てないと成功しにくい。・人が集まる人気のエリアはそもそも好条件の出店場所が無い。2.オフィス街「オフィス街」のメリット・特に会社員のランチ(ディナー)タイムに大きく売り上げが見込める。・集客できる曜日、時間帯がピンポイントなので戦略が立てやすい。・店内以外のテイクアウトや移動販売で売り上げを伸ばしやすい。「オフィス街」のデメリット・夜間や休日は人が離れているので、集客が見込めない。・ピークが会社員の休憩時間に限られるので、提供スピードなど回転率が重視される。・賃料が高く、ビルが立ち並ぶエリアはそもそも小規模の店舗が出店できない。3.住宅街「住宅街の出店」のメリット・賃料などランニングコストを安く抑えることができ、それ以外にコストがかけられる。・競合店が少なく、近隣住人(常連)の需要を見込みやすい。特にテイクアウトやデリバリーはコロナ禍で在宅勤務が増えていることも追い風になります。・地域に溶け込むことで住民同士の口コミ、交流などコミュニティが形成できる。「住宅街の出店」のデメリット・アルバイトなど人員の確保が難しい。・地域住人以外が利用する可能性が低く、通りすがりの来客が見込めない。・昼間は仕事に出ている人が多く、ピークの時間帯が限られる。・少数の来客が多く、宴会など大人数の集客はなかなか見込めない。それぞれのメリット・デメリットなど特性を理解した上で、自身がどんな業種でどんなお客さんに来てもらいたいかなど、作り上げたい店舗像を具体的に考えてみましょう!
-
トラナビ通信2022.08.03
原油価格の高騰にどう対応するか
昨今、様々な業界で値上げラッシュが続いています。原油価格の高騰に伴う物流費や原材料費の値上げが大きな原因ですが、その他にも天候不順による野菜の不作であったり、飲食業界にとってもかなりの打撃となっています。値上げすることが悪ではありません。原価が上がれば当然利益も下がりますから、お店を続けるためにも利益は確保していかなければなりません。上げないから偉いとかではなく、上げることは普通のことで、ここはフラットに考えていただきたいです。とは言えです。値上げしました“だけ“ではお客さんにとってマイナスでしかありません。値上げで苦しいのは食材や日用品に影響がある一般家庭でも一緒です。なので、即値上げの前に今の自分たちができることを考える必要があります。例えば、現状かかっている経費やロスを減らすところから考えます。その一つとしてメニューを見直すことがあげられます。例えば、出食数のABC分析だけ行って、原価の高い割に人気の無い料理は思い切って削るなどです。SDGs(持続可能な目標)の取り組みの中にある、フードロスを減らすことにもなるので、積極的にやっていただきたいですね。あとは、付加価値です。付加価値とは、独自の価値を商品やサービスなどに付け加えることを言います。例えば、居酒屋であればちょっとお洒落なグラスやお猪口に一新してみるとかですね。お客さんが「やっぱりいいグラス(お猪口)で飲むと美味しいな!」と言ってもらえたら、それは立派な付加価値になります。親切なサービス、従業員の魅力、お洒落な内外装など、全てこれに該当します。少し嫌らしい表現にはなってしまいますが、”飲食店大変だけど色々考えて頑張ってるな”と感じていただければ、そのお店を応援しようと2度3度と自然に足を運んでくれるようになるはずです。それが伝われば値上げのハードルなんていうのは、それ程大きな問題にはならないと私は考えます。是非、経費の見直し・付加価値を創る。この2点は特に意識して取り組んでいただきたいと思います。
-
トラナビ通信2022.07.27
飲食店の開業資金いくらかかる?
今日は、これから飲食店の開業を行おうと考えている方に、避けては通れない「お金」の話をしようと思います。飲食店の開業を目指す方なら聞いたことあると思いますが、開業を一から全て自分で行うとなると、物件の保証金や敷金・内外装・厨房設備・備品・宣伝広告・メニューや看板に、レジやパソコンなどなど。規模にもよりますが、1000万円程度は必要になると言われています。これがいわゆる「開業資金」です。ただ、これだけ用意すればお店を始められる訳ではありません。これに加えて「運転資金」というお金が必要です。いざ出店しても、お店を維持するために必要な資金はたくさんあります。家賃・水道光熱費・仕入れ・人件費・通信費・広告費など、これらを出店してみないと確定しない売上で最初から賄おうというのは無茶な話です。「絶対売れる自信があるから大丈夫!」その前向きな心意気やよし。ただ、ポジティブに物事を進めるためには必ず十分な準備が必要です。それが事前の計画であり、資金であり・・立ち上げてからこんなはずじゃなかったという後悔は誰もしたくないはずです。なので、少なくとも3~6ヶ月程度、維持できるだけの資金は確保しておきましょう。もちろん多ければ多い程良いです。余裕があればこそ、打てる策がありますからね。ただそれだけのお金、自己資金だけでどうにかできるのは一握りの人です。なので、借り入れなど資金調達をすることになりますが、結局お金を借りるにもその信用を得るだけの根拠を準備しなければなりません。この準備が色々と大変なんですよね。根拠資料を基に自分の計画を売り込まないと当然十分な資金は得られません。ここまで自分で全て準備してお店を開くことについてお話しましたが、開業ひとつとっても世の中には様々な手段があります。フランチャイズの様に初期投資を抑えて、提供されたノウハウやブランドで事業を行ったり、クラウドファンディンで自分の売りをアピールすることで必要資金を補ったり、共同経営で資金を出し合って一緒にお店を始めたり・・他にも開業費用を一切かけずに、ご自身のやりたいお店を自由に作り上げる方法もあります。そんな方法あるなんて知らなかった、なんて声をいただくことも多いので、開業をお考えの方は是非一度ご相談ください!
-
トラナビ通信2022.07.20
待っていても客は来ない
皆さんは“広告”と聞くと、どんなイメージを持たれますか?お金をかけて何かに掲載するものと認識される方も多いのではないでしょうか。今日お話したいのは、SNSについてです。Twitter、Facebook、Instagram、最近だとTickTokもユーザーが増えていますね。これらを総称してSNSと呼びます。あれ?広告の話じゃなかったの?SNSってただ単に自分の好きなことや起こった出来事を周りに発信するツールじゃ・・そう思っていませんか?いやいや、SNSは立派な広告媒体なんです。私がこれまで見てきた飲食店の経営者で、SNS(インターネット)とか良く分からないから必要ないよ!という方もいらっしゃいました。昔に比べて大分減ってはきましたけどね。ひと昔前、デスクに座ってパソコンで調べないと情報が分からない時代もありましたが、今は、ポケットにパソコン(スマホ)が入り、いつでもどこでも情報にアクセスできる時代です。外食しようとする時、食べログやGoogleの口コミ、SNSやホームページなどで吟味してから決めるお客さんはとても多いです。SNSを活用すると多くのメリットがあります。例えば―・今すぐにでも始めることができる・無料でお店を宣伝ができる・お客さんの生の声が聞ける・お客さんが勝手にお店の宣伝をしてくれる・SNS目当てのファンを獲得できる対照的にデメリットもあります。・投稿内容によってはお店のイメージダウンになる・継続が大変&止めてしまうと逆効果になる・ファンが付くのに手間と時間が掛かるうまく活用できれば、どんどんお店をアピールできる反面、マメな投稿を意識しないといけないという点はありますね。ただSNSは、「無料」で店舗の魅力を「大勢」の人に「リアルタイム」でアプローチできるとても優秀な媒体です。つまるところ、無料で使えるのに活用しないと勿体ないよ!というお話です。まだ手を出せていない方は是非、お店をアピールするツールのひとつとしてチャレンジしてみてはいかがでしょうか?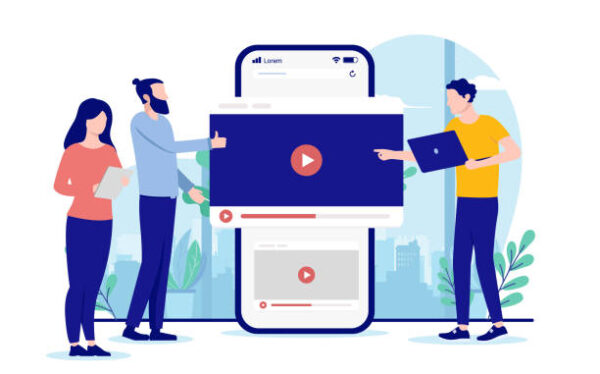
-
トラナビ通信2022.07.13
トラナビ通信更新スタート!
トラナビでお店の開業をサポートしている金子です。飲食店を開業される方のヒントになるよう、トラナビ通信を更新していくことになりました!本日は、飲食店のQSCについて。QSCとは、Q:クオリティ(品質)S:サービス(接客)C:クレンリネス(清潔さ・身だしなみ)と、飲食店においての重要ポイントのことです。それに加えて、最近ではH:ホスピタリティも重要視されています。H:ホスピタリティは、わかりやすく言うと「気配り」のこと。例えば、・おしぼりの香りにも気を配っている・お水を注文された時に、どういった用途かによって、氷有無、白湯かを見極める・女性客にはひざ掛けが用意されている・お子さんがいらっしゃる場合は、① 「量を減らすこともできますよ」と声をかける② ベビーカーの移動を手伝う③子ども用の食器を用意する④帰りに駄菓子をプレゼントするなどなど。要は、これから起きることを想定できているか?お客様が考えそうなことを先読みできるか?これが大事!店員の目線と、お客さんの目線って結構違うんですよね。若いサラリーマンとかだと料理が来るまでスマホを見てたりするんですが、中高年になると何をしてるかというと、店の中をぼーっと見てる人、多いんです。そんな時に、「あれ?あのお客さんの上、塗装が剥がれ落ちそう」なんて思ったら、自分のところは大丈夫だろうかと思わず上を見てしまいますし、結果的にお店の印象はマイナスになりますよね。わたくし、金子も普段色んなお店を見て回っていますが、やはり、来客数が徐々に落ちているお店は、こういった小さな気配りができてなかったり、明らかに早く改善した方がいいことに気づいていなかったりするお店がほとんどです。QSCに加え、Hまで完璧に行うには、まさに頭の後ろにも目を持つくらいの緊張感が必要です。ただ、これも慣れ。習慣化してしまえば、お店の経営だけでなく考え方も変わってくるので、ぜひ、実行していきましょう!トラナビでは、現在、広尾や自由が丘でお店を出したいという人を募集しています。とても好条件の立地での開業になるので、現在の資金では理想のお店が開けないという方、ぜひトラナビにご応募ください。
